AOIについて
合格実績
授業内容
料金プラン
入試情報
お問い合わせ・質問
AOIについて
合格実績
授業内容
料金プラン
入試情報
お問い合わせ・質問
作成日: 2024年5月20日 最終更新日: 小論文対策

こんにちは!総合型選抜専門塾AOI編集部です!
小論文は、大学受験に合格をする上で非常に重要です。
そのため、こんなお悩みを持っている人も多いのではないでしょうか?
「小論文を解いたことがない」
「大学受験で小論文が必要」
「小論文の書き方、構成、例文が知りたい」
今回は、情報学部を専攻したい高校生に向けて、小論文の書き方を専門家の視点で詳細の解説していきます。
一番詳細に記載されている記事かと思いますので、この記事をきちんと読んで理解すれば、あなたは必ず小論文の文字数を埋められるようになるでしょう。
また、 AOIでは期間限定で総合型選抜の対策に関するプレゼントを無料で10個もらえるキャンペーンを行っています!
AOI公式LINEで配布しているのでぜひ受け取ってください!
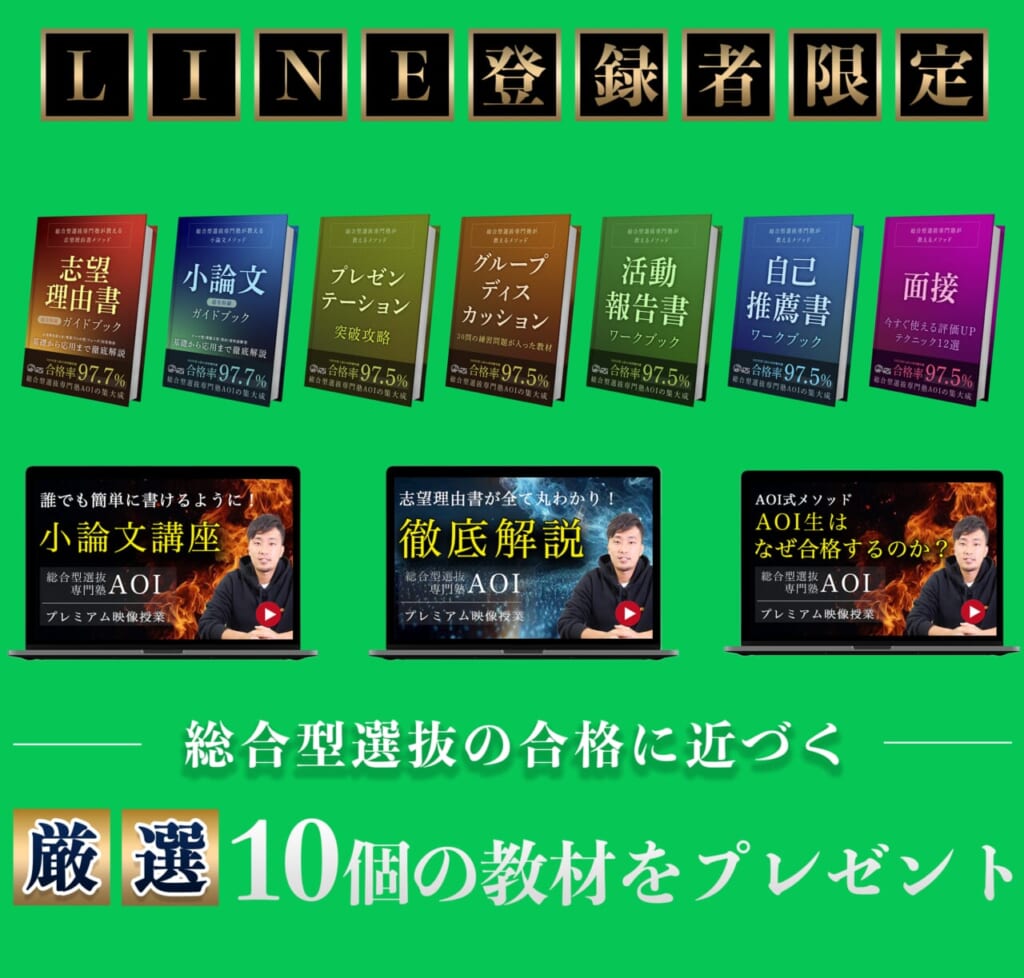

まずは、小論文とは何か?を復習していきましょう。
小論文とは、自分の意見を論理的に整理し、説得力を持たせて記述する文章です。
客観的な事実やデータを用いて、自分の主張を明確に伝える必要があります。
設問の形式は、テーマ型や資料読解型など多岐にわたります。
作文とは異なり、小論文では主観的な感想は避け、論理的な構成と根拠の提示が重視されます。
小論文のルールについて説明します。
まず、設問に対する自分の意見を明確にし、論理的な根拠を示すことが重要です。
構成は「序論、本論、結論」の三段階に分け、各段落を明確にしましょう。
原稿用紙の使い方も重要で、段落の始めは1マス空けること、数字は1マスに2文字書くことが基本です。句読点や記号の使い方にも注意し、文を短く、読みやすくすることが求められます。
小論文は客観的かつ論理的な表現が重視されます。
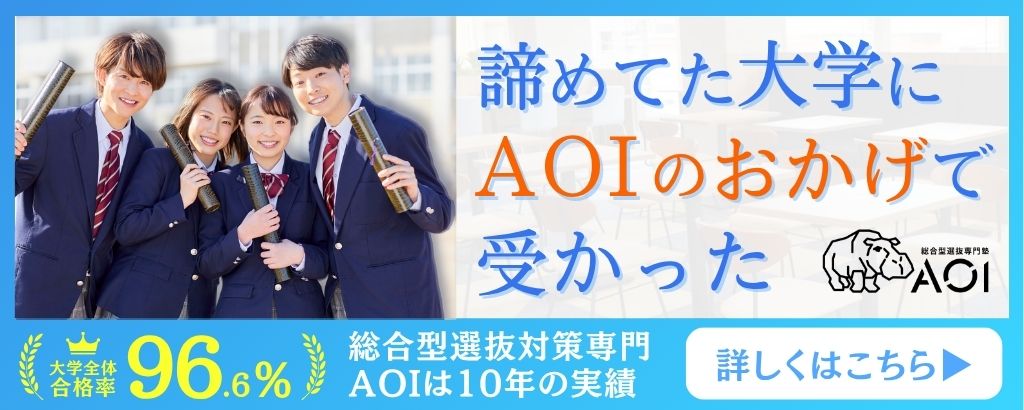
次に、小論文の評価項目や構成について解説します。
⚫︎論理的思考力
主張から結論まで一貫しているかを評価します。論理の飛躍がないかも重要です。
⚫︎知識力
解決策や具体例における知識の質を評価します。情報が正確であるかを重視します。
⚫︎日本語力
語彙力や表現力、段落構成を評価します。読みやすく正確に伝えることが求められます。
⚫︎設問理解
設問のテーマや条件を理解し、適切に答えられているかを評価します。
小論文は「序論」→「結論」→「本論」の順番で書くことがオススメです。
理由としては、この構成が一番「主張」を論理的にわかりやすく伝えられると言われているからです。
それでは、序論→結論→本論の順番で確認していきましょう。
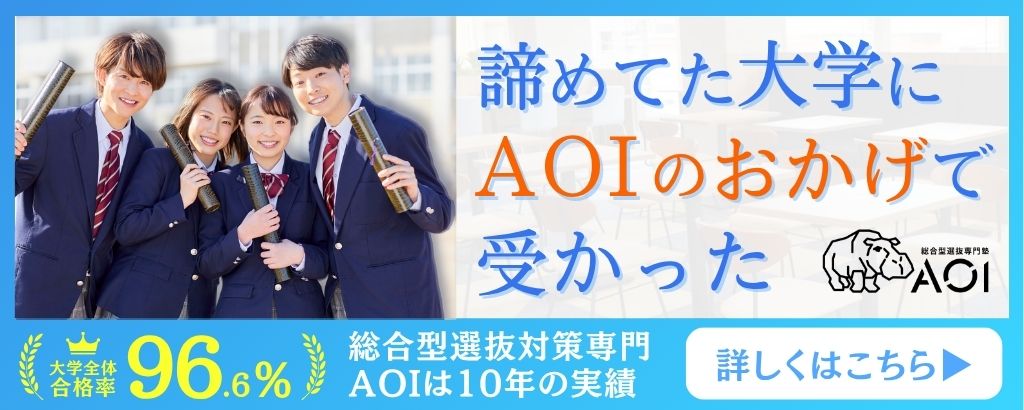
序論とは、小論文の書き出し(書き始め)のことを指します。
序論では、あなたの主張と根拠を簡潔にまとめましょう。
これからあなたがどのような話を展開するのかをわかりやすく理解してもらうことが重要です。
本論は、序論で簡潔にまとめた主張を詳細に説明していく箇所となります。
ここでは、あなたの知識を用いながら、なぜ序論の主張をするに至ったのかを説明していきます。
客観的な意見にまとめることが重要です。
結論は論文のまとめであり、主張を強調し、読者に論文の重要なポイントを振り返らせる役割を果たします。
ここで、重要なことは今まで話していなかった関係のない他の話をあえてしないことです。
そのため、基本的には序論と似たような内容となります。
それでは、小論文を書いてみましょう!
SDGsにおいて最も重要な課題は何か?
その課題の解決に向け、具体的な提案や行動を400文字で述べよ。
制限時間:30分|文字数:400文字
地域社会におけるSDGsの浸透度や理解度が低い状況において、どのようなアプローチが有効か?地域住民への啓発や協力を促進する手段について検討せよ。
制限時間:40分|文字数:800文字
企業においてSDGsの達成に向け、具体的な施策や経営戦略が求められている。
企業がSDGsを組織戦略にどのように組み込むべきか、その実践例について考察せよ。
制限時間:50分|文字数:1200文字

小論文には、4つの出題形式があります。
「実践編!3つの小論文を解いてみよう」は、テーマ型と言われる小論文になります。
テーマ型以外にも、3つの型があるので、理解しましょう。
課題文型小論文とは、テーマ型とは異なり、課題文(2000字以上)を読んで設問に答えていく小論文です。
課題文型小論文で求められていることは、読解力と思考力です。
課題文からどのようなことが重要なポイントなのかを掴み、それに対して説得力のある意見を主張することができるのかということが大事になっています。
グラフ/資料読み取り型小論文とは、グラフ等の資料が与えられ、それに対して設問が与えられる小論文です。
課題文型小論文で求められていることは、読解力と分析力です。
グラフや資料の内容を正確に理解したり、重要なポイントを見極め、データの意味を分析したりすることが重要です。
『さらに詳しく、グラフ/資料読み取り型小論文の書き方を知る!』
講義型小論文とは、大学の教授が何らかのトピックに対して講義をした後、講義をふまえて出題された設問に答える小論文です。
講義型小論文で求められるのは、読解力と論理的思考力です。
講義の内容を正確に理解したり、講義内容を整理し、論理的に説明したりすることが重要です。
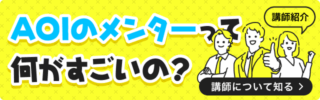
総合型選抜/学校推薦型選抜(公募制推薦.指定校推薦)で情報学部を受験する際には、
必ず5つの頻出テーマを人に説明できるようになりましょう。
1.AIと社会
AIの進化は社会構造を根本から変える可能性があります。
特に、労働市場における自動化、医療分野での診断支援、金融におけるリスク分析などが重要なテーマです。
また、AI倫理の課題も重要で、AIによる意思決定の透明性と公平性をどう確保するかが問われます。
重要キーワード
深層学習(ディープラーニング)、自然言語処理、AIガバナンス、倫理的AI、透明性
2.ビッグデータとデータサイエンス
ビッグデータは、様々な分野での意思決定を支える重要な資源となっています。
データサイエンスでは、大規模データの収集、保存、解析、可視化技術が不可欠です。
機械学習アルゴリズムを用いて予測モデルを構築し、ビジネスや医療、環境保護に応用します。
重要キーワード
クラスタリング、回帰分析、時系列解析、ビジュアライゼーション、スケーラビリティ
3.情報セキュリティとプライバシー
デジタル化が進む現代社会では、情報セキュリティの確保が最優先課題です。
暗号化技術、ネットワークセキュリティ、侵入検知システムなど、技術的対策が求められます。
また、プライバシー保護法規制への対応や、データ漏洩に対する迅速な対応策も重要です。
重要キーワード
暗号プロトコル、ゼロトラストセキュリティ、侵入検知システム(IDS)、個人情報保護法(GDPR)
4.ヒューマンコンピュータインタラクション (HCI)
HCIは、人間とコンピュータのインターフェースを最適化するための学問です。
認知心理学、ユーザビリティテスト、インタラクションデザインなどの技術を駆使し、使いやすさと効率を追求します。拡張現実(AR)や仮想現実(VR)も注目分野です。
重要キーワード
ユーザセンタードデザイン(UCD)、認知ロード、プロトタイピング、AR/VRインターフェース、ユーザエクスペリエンス(UX)
5.IoTとスマートシステム
IoTは、物理的なデバイスをネットワークで接続し、データ交換を行う技術です。
スマートホームやスマートシティの実現には、センサー技術、リアルタイムデータ解析、エッジコンピューティングが鍵となります。エネルギー管理や交通制御など、多岐にわたる応用が可能です。
重要キーワード
センサーネットワーク、リアルタイム処理、エッジコンピューティング、スマートインフラ、サイバーフィジカルシステム(CPS)
以上のテーマとキーワードを深く理解し、具体的な事例やデータを用いて論じることで、総合型選抜の小論文対策を効果的に行うことができます。
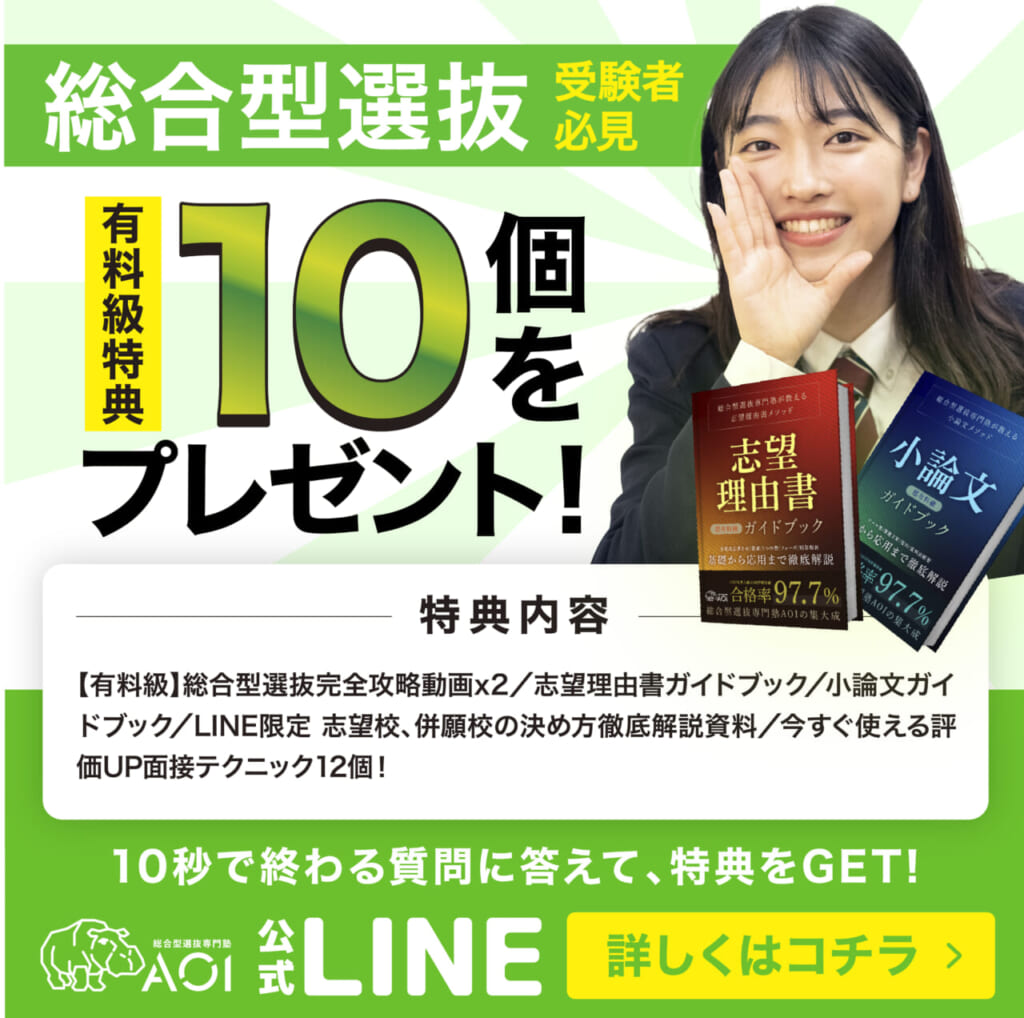

情報学部の小論文では、科学的思考力と高度な論理構築力が求められます。
以下の5つの頻出テーマを理解し、関連する専門用語を押さえましょう。
具体的な知識や事例を基に、自分の見解を論理的に展開する練習をしましょう。
1.AIと社会
AIの進化とその社会的影響について理解しましょう。
特に、労働市場/医療/金融などの具体的な応用例を知ることが重要です。
最新のAI技術や事例を調査し、それが社会に与える影響を具体的に説明できるようにしましょう。
AI倫理についても考察し、バランスの取れた意見を持ちましょう。
2.ビッグデータとデータサイエンス
データ解析技術とその応用について理解を深めましょう。
特に、データ収集方法や解析手法についての知識が重要です。
ビッグデータの具体的な事例を研究し、データサイエンスの基本概念と技術を学びましょう。
3.情報セキュリティとプライバシー
情報セキュリティの基本原則とプライバシー保護の重要性を理解しましょう。
具体的な技術や法規制について知識を深めましょう。
セキュリティインシデントの事例を調査し、対策方法を学びましょう。
暗号化技術やセキュリティプロトコルの基本を理解し、最新の法規制にも目を通しましょう。
4.ヒューマンコンピュータインタラクション (HCI)
HCIの基本概念とユーザーエクスペリエンス向上のためのデザイン原則を理解しましょう。
特にインターフェースデザインの重要性を学びましょう。
認知心理学やユーザビリティテストの方法を学び、実際のアプリケーションやデバイスのインターフェースを評価できるようになりましょう。
5.IoTとスマートシステム
IoT技術とその応用分野について理解を深めましょう。
特に、センサーネットワークやエッジコンピューティングの役割を学びましょう。
IoTシステムの構築事例を研究し、センサー技術やデータ解析手法を学びましょう。
スマートシティやスマートホームの具体例を通じて実践的な知識を身につけましょう。
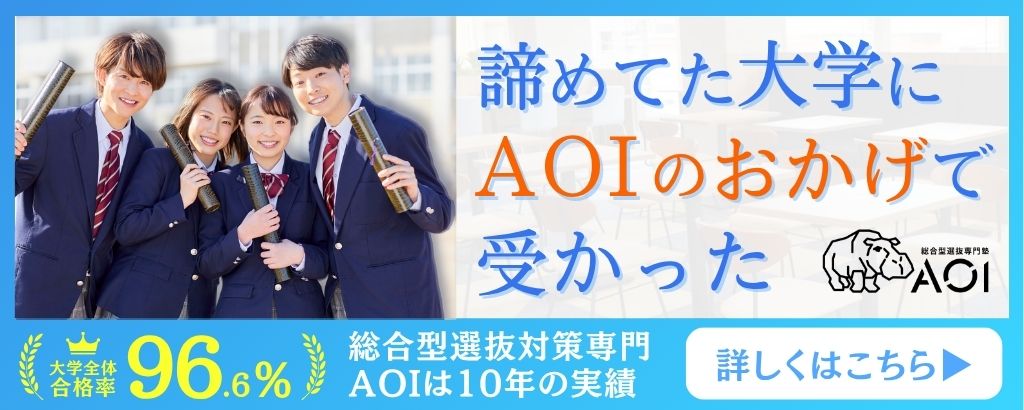
それでは、過去問題とその解答例を参考に、小論文がどのように評価されるか理解していきましょう。
設問
近年、政府にもっと積極的な情報公開を求める声が高まっている。その一方で、政府がなんでも情報を公開するのは 問題が多いので、慎重に考えるべきだという意見もある。あなたはどう考えるか論じなさい。
回答例
政府は情報公開に対して必要最小限度に留めるべきであると考える。理由は、行政にはその長の裁量が広く認められるべきだからだ。
情報公開制度の根拠は、国民の知る権利にある。個人が自己の人格を形成する、また民主主義社会における主権者として自由に議論するためにも情報の受領は非常に重要であると言える。
しかし、行政権の円滑な遂行のためにも行政に裁量を広く認めるべきだ。みだりに情報を公開しては、個人や法人の情報が漏れ、その人権を害する恐れがある。また、不確定な情報の開示はかえって国民の判断を乱し不利益に繋がるだろう。だからこそ、情報公開に際しては、行政が、公開の可否や公開するにしてもどこを公開するか慎重に判断する必要があり、国民の要請に迎合するべきではない。また、正しい情報を流すことこそが国民の知る権利の要請に合致しているといえよう。
以上より政府は情報公開を必要最小限度に留めるべきである。
⚫︎論理的思考力
この模範解答は、情報公開の必要性とその制限についてのバランスの取れた視点を示しています。
まず、情報公開の重要性を認めた上で、行政の円滑な運営のために情報公開を制限する必要性を説いています。
この二重の視点が、論理的な構造を形成しており、説得力があります。
⚫︎知識力
解答は「国民の知る権利」や「行政権の円滑な遂行」などの専門用語を用いており、情報公開制度の背景にある法律的・社会的な知識を示しています。
また、個人や法人の情報保護、不確定な情報の問題など、具体的なリスクについても言及しており、知識の深さが伺えます。
⚫︎日本語力
文章は明確で簡潔です。
専門的な内容をわかりやすく伝えるために、適切な文脈で専門用語を使用しながらも、難解な表現を避けています。
文の構造も一貫しており、読者が内容を理解しやすいように配慮されています。
⚫︎設問理解
設問に対する答えは明確で、一貫しています。
情報公開の必要性とその制限の必要性を論じており、設問の要求に的確に応えています。
また、賛成と反対の両方の意見を考慮し、最終的に一方の立場を明確に示しています。
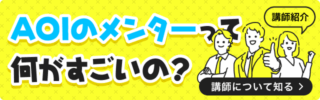
それでは、これまで学んだことを踏まえて、実際に情報学部に関する小論文に取り組みましょう。
デジタル社会の進展により、私たちの生活は便利になりましたが、一方でサイバーセキュリティの脅威も増大しています。この利便性とリスクのバランスをどのように取るべきか、あなたの考えを述べなさい。(制限時間:30分|文字数:400文字)
人工知能(AI)が日常生活や労働市場に与える影響について述べ、AIと人間が共存するための社会の在り方についてあなたの意見を示しなさい。
(制限時間:30分|文字数:400文字)
近年、ディープフェイク技術が進展し、偽情報が広がるリスクが高まっています。ディープフェイクの課題を明らかにし、その対策についてあなたの考えを示しなさい。(制限時間:50分|文字数:1200文字)
小論文を書くのは難しいですよね。
特に、倍率の高い大学では、求められるレベルが非常に高く、
「どのように書けばいいのかわからない」
「添削してもらう時間がない」
といった悩みを抱えている方も多いのではないでしょうか?
実際、私たちも多くの受験生から同じような声を聞いてきました。
自分だけで小論文を書くのは不安が大きく、何度も書き直すうちに時間だけが過ぎてしまうこともありますよね。
そこで、AOIが使用している教材『小論文ガイドブック(pdf形式)』を無料でプレゼントすることにしました。
このガイドブックは、短期間で効果的に小論文を書くための具体的な方法と、実際に合格した例文を収録しています。
このガイドブックを利用することで、最短で合格する小論文を書けるようになります!
今なら先着50名様に無料でプレゼントしていますので、ぜひこの機会にご利用ください。特に、小論文に苦手意識を持っている方や、短期間で小論文のスキルを向上させたい方に最適です。
このガイドブックを使って、効果的に小論文の書き方を身につけましょう。
今すぐ下記の「友達追加」ボタンをクリックして、『小論文ガイドブック』を受け取ってください!
先着50名様に達し次第、配布を終了しますので、お早めに受け取ってください。
なお、教材を受け取るだけでは合格には近づきませんので、
学校の先生や親御さんにも読んでもらい、正しい添削をしてもらいましょう。
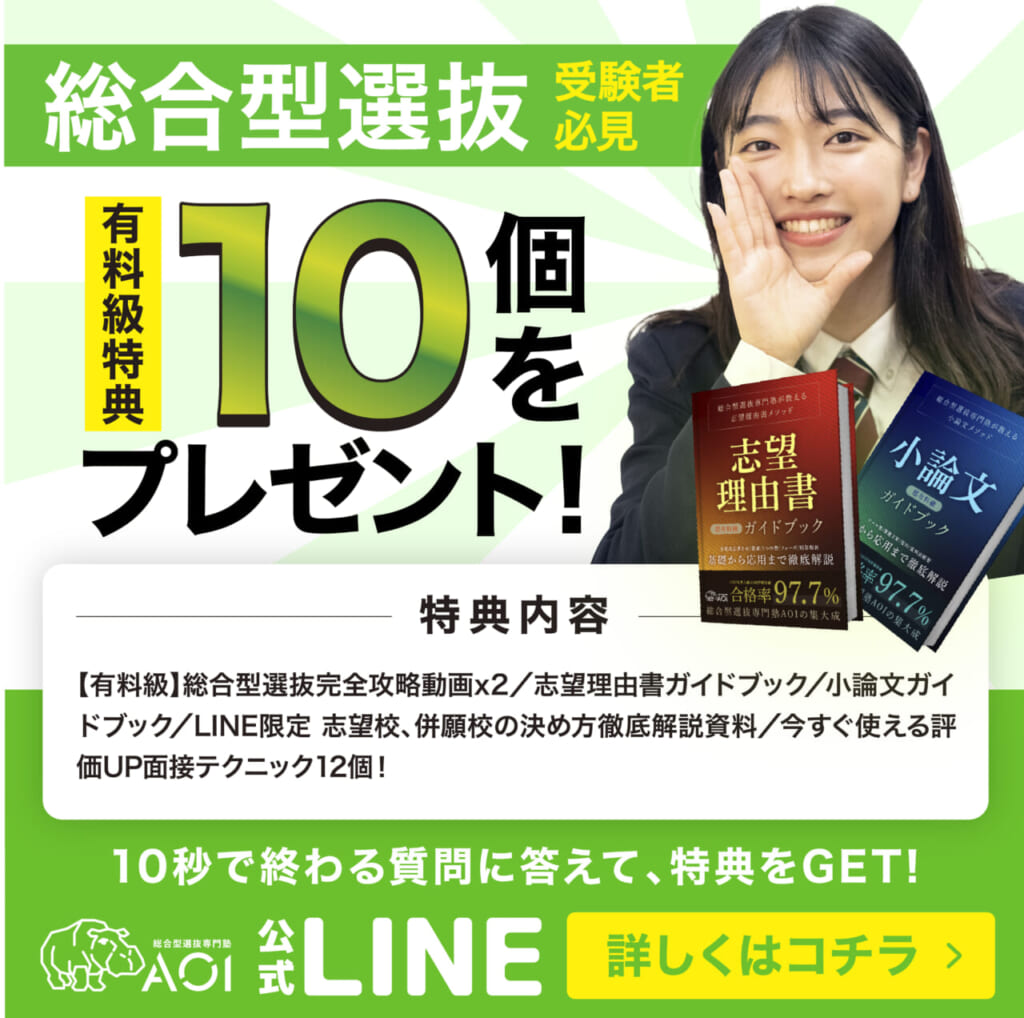

ここまで読んでも小論文が書けない人のためにレベルアップする4つの方法をお教えします。
小論文の上達方法は、4つです。
小論文の参考書を読むことは非常に大切です。
合格者のほとんどは参考書を当たり前のように呼んでいます。
AOIからも小論文の本を出していますので、ご検討ください。
関連記事:『小論文対策のポイントとオススメの参考書を専門塾が徹底解説!』
自分の書いた小論文を他の人に添削してもらうことは、改善のための重要なステップです。
添削を受けることで、自身の弱点や改善点を特定し、スキルを向上させることができます。
以下は添削のポイントです
1.塾や教師に添削してもらう
大学受験の専門家や小論文に詳しい学校の先生に添削を頼むことで、専門的なアドバイスを得ることができます。
また、小論文の対策を行う推薦入試の専門塾に入れば、その他の対策も並行して進めることができます。
総合型選抜/学校推薦型選抜を検討している人は、総合型選抜/学校推薦型選抜の専門塾に入りましょう。
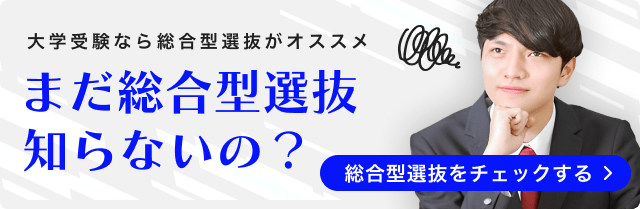
2.有料添削サービスを活用する
添削は、塾や学校の先生以外も行ってくれます。
以下の記事で添削サービスを紹介しています。
関連記事:『小論文添削をしてくれるおすすめの添削サービスを紹介』
小論文を書くためには、広範な知識や情報が必要です。
関連する本、学術論文、記事、ニュースなどの情報源から学習を深め、トピックに関する知識を積み重ねることが重要です。
以下は知識を読む際のポイントです:
- ニュースサイトを活用する: 同じテーマについて異なる視点や情報を提供する情報源を探し、多角的な理解を深めます。
- 文献リサーチ: 学術的な小論文を書く場合、信頼性のある文献を調査し、引用するための正確な情報を収集します。
推薦図書:『7日間で合格する小論文-読み方&書き方を完全マスター』
AOIでは、公式LINEをお友達追加してくれた人限定で10個の特典を無料でプレゼントしています!
10秒で終わる質問に答えると
・【有料級】総合型選抜完全攻略動画x2
・志望理由書ガイドブック
・小論文ガイドブック
・プレゼンテーション解説資料
・今すぐ使える評価UP面接テクニック12個!
etc..
など有料級特典合計「10個」をプレゼント!
これらの無料教材を通して、自身で添削できるになりましょう。
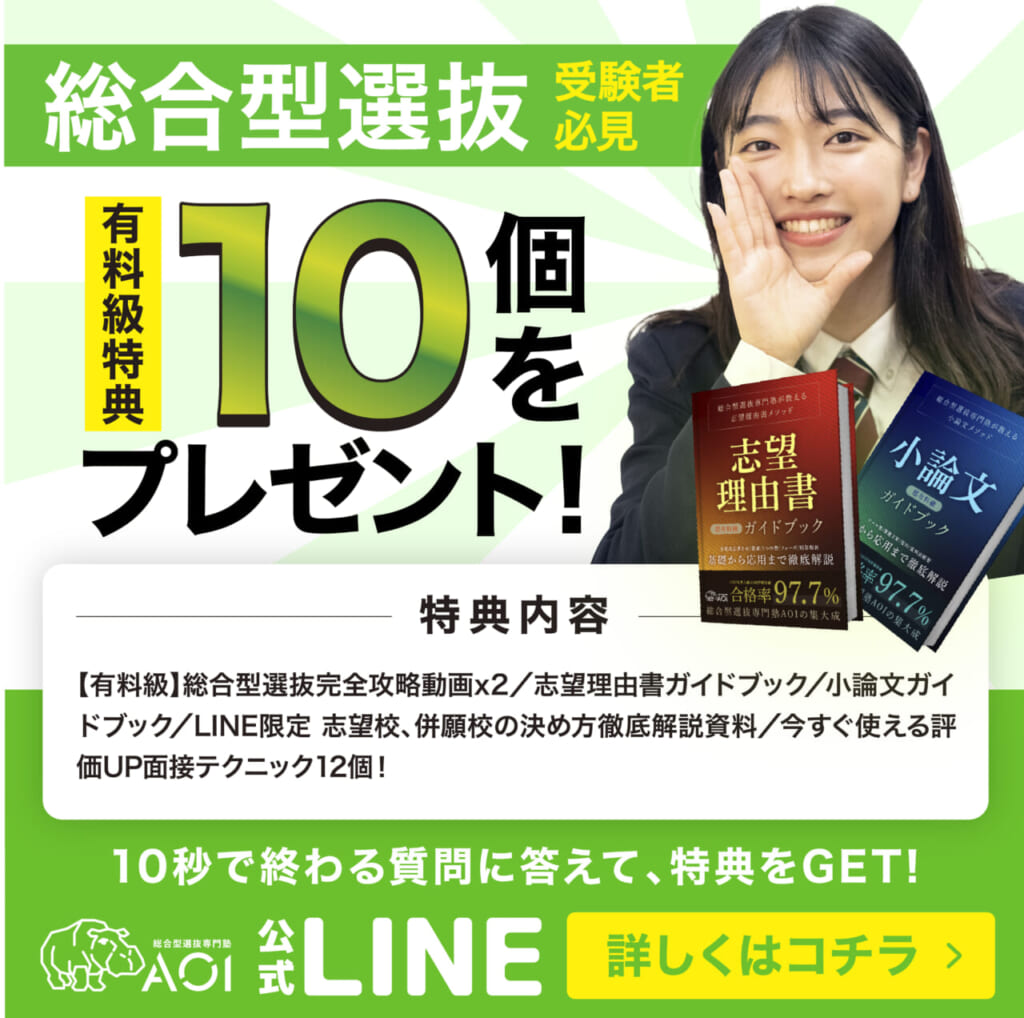

これらの事前対策を実施することで、小論文のスキルを向上させることができます。
小論文対策は大学受験において非常に重要な要素の一つです。
そのため、なるべく塾で指導を受けることをオススメします。
適切な塾選びと指導を受けることで、小論文スキルの向上や志望校合格に大いに貢献します。
自身の状況に合わせて、最適な小論文対策を進めましょう。
AOIの専門家があなたが合格できるようにアドバイスをさせていただきます。
まずはあなたの小論文に関するお悩みを受験相談で聞かせてください。
それでは、お待ちしております。
私たちと一緒に憧れの志望校に合格しましょう!
下の画像をタップしてお申し込みください!

【最後に】
受験相談は、大変人気となっております。
受験相談の枠は、現時点で約9割(※自動更新)が埋まっています。
申し訳ありませんが、お申し込み時期によっては、全ての枠が埋まってしまい受験相談を実施できない 恐れがあります。
そのため、できるだけ早く無料受験相談にお申し込みいただくことを、推奨しております。